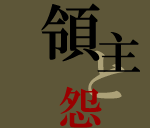スナバコ

「二人と茶会」校正メモ(上が新しく、下が古い)
恐れぬただ一人である女領主は、緩く吐く息に過去を乗せる。
女領主はそれきり、唇を静かに結ぶ。
常に赤茶の目に水鏡の如き静けさを湛え、淡々と相手する。
それだけで、膝に重ねる手、風が遊ぶに任す濃紺の髪、閑散とした庭に向ける眼差しは微塵も変わらない。
親しみやすく振る舞う様は、おおよそ呪術師らしくない。
怪我や病気でもしてなければ、この季節は夜まで放牧に出すのが常だ。
呪術師の高く澄んだ声が、領主の間に近い客間から流れる。
呪術師の高く澄み、すぅっと消えていく声は、耳に心地よい。
(因果なこともあるものよ)
風を紡ぐように、吐く息に過去を乗せる。
恐れぬ女領主は、
呪術師の高く澄んでいて、それですぅっと消えていく声は、耳に心地よい。
親しみやすく振る舞う様は、呪術師のものとは言い難い。
(やれ。旅歌いのようだ)
館の皆が不安がっていることは、女領主も承知している。無暗に忌諱すべきでないとしたのは、彼女の個人的な方針だった。
されど、無暗に忌諱すべきでないというのが彼女の方針だった。
女領主は終えて、唇をきゅっと結ぶ。
親しみやすく振る舞う様は、おおよそ呪術師らしくない。
女領主は、答えず中庭を眺め続ける。
彼女は呪術師を丁重に扱うも、蔑ろにするもなく、常に赤茶の目に水鏡の如き静けさを湛え相手する。
呪術師が気に掛ける笛は、時につっかえるようで、時に駆け走るようで、いかにも覚束無い。
女領主は呪術師を丁重に扱うも、蔑ろにするもない。
問われた女領主は泰然とし、赤茶の目に水鏡の如き静けさを湛えている。紡ぐ言葉も一拍の後、静かに零れた。
夕暮れの近づく頃、円回廊の館に家畜が少ない。
女領主は聞くことはなしに、赤茶の目に水鏡の如き静けさを湛えている。紡ぐ言葉も一拍の後、静かに零れた。
「この掛け合いの旋律は、どのような方の奏ででしょうか」
中庭向きの戸は全面取り払われ、放たれし声は晴天の青へ消えた。
怪我や病気でもしてなければ、この季節は夜まで放牧に出すのが常だった。
夕暮れの近づく頃、円回廊の館には家畜が少ない。
気配に微塵も変わるところなく、濃紺の髪を風が遊ぶに任せる。
のんびりとした口調で、句が重ねられる。
女領主の気配に、微塵も変わるところはない。
こうして呪術師の他愛ない問いに応えてやるのも、随分日常と言えるようになった。
呪術師の声は再び女領主へ向かう。
呪術師が訪ねてきて六度目になるが、これも彼の他愛ない問いの度のこととなっていた。
そして聞き様によっては不機嫌とも取れる女領主のそれを、呪術師は気にすることもまたなかった。
女領主は呪術師を丁重に扱うこともなく、また蔑ろにすることもない。
こうして呪術師の問いに応えてやるのも、随分日常と言えるようになっていた。
女領主は聞くことはなしに聞いている。赤茶の目は館の内に留まり、水鏡の如き静けさが湛えられていた。
ようやく口の当て方を覚えた、幼い奏者らしい音色が流れている。
遠き笛は、時につっかえるようで、時に駆け走るようで、いかにも覚束無い。
女領主の赤茶の目は、館の内に留まっていた。そこには水鏡の如き静けさを湛えており、紡ぐ言葉も一拍の後、静かに零れる。
ようやく口の当て方を覚えた、幼い奏者のものと思えた。
中庭向きの戸は全面取り払われ、放たれし音は晴天の青へ消えた。
夕暮れの近づく頃、円回廊の館には家畜の数が少ない。
言葉には抑揚も少ない。
水鏡の如き静けさを湛え、音を紡ぐも一拍の間の後のことである。
怪我や病気でもしてなければ、夜が近づくまで放牧に出されるのが常だった。
女領主の隣に座すは、目が隠れるように頭巾を被り、黒っぽい装束に身を包んだ男。
ルシヤの館は円回廊とも呼ばれる。大きな円形の中庭を、屋根が柵のように囲むことが由来だ。
夕暮れも近づいた時刻、庭には鶏と怪我や病気、お産が近い羊や山羊が何頭かいるのみ。外の濃い気配に比べ、庭は静かだった。
遠くの笛の音は、時につっかえるようで、時に駆け走るようで、いかにも覚束無い。
女領主は水鏡の瞳をして、一拍の間を置いて応える。
呪術師の高く澄んだ声は、再び女領主へと向かう。
案内したのは領主の間に近い客間で、中庭向きの戸を全面取り払っている。
回廊には子どもの一人すらいない。故に、人の声はこの客間からのみ響く。
「ああ、秋祭りの笛が聞こえますね」
女領主の隣に座る男は、目が隠れるように頭巾を被り、黒っぽい装束に身を包んでいる。ウル=ルシヤ峠前の怪我人は、すっかりただの呪術師に戻っていた。
あやつらも、秋に神へ奏上することになろう
呪術師の眼は女領主へ向く。
女領主は高く澄んだ声の呪術師に、一拍の間を置いて応える。
故に、人の声はこの二人のもののみだった。
あやつらも、秋に初めて神へ奏上することになろう
七にもなる頃、たいていは父に、奏者やら踊り手、祈祷師などの作法を習う。
ようやく旋律を紡ぐことを学び始めた、幼い奏者のものと思えた。
ようやく笛の音を出せるようになった、幼い奏者のものと思えた。
遠くの笛は、時につっかえるようで、時に駆け走るようで、いかにも覚束無い。
回廊には子ども一人近寄らず、故、人の声は子の二人のもののみだった。
初物奏上ですね。
あやつらも、秋に初めて神へ奏上することになろう
「初物奏上ですね。ケニさんの時には、何人で奏上されましたか? 他の集落では、たいてい、2人か3人と聞きますが。」
「あしのときは、9人じゃな。あの年は多くなった。今年は、4人あればいいが。」
呪術師は随分のんびりと、遠くの笛のについて聞いていた。
呪術師が館の南東の、ここから右奥の場所へ目を向ける以外は。
回廊には子ども一人近寄らない。この、けったいな客のためだ。
女領主の隣に座る男は、目が隠れるほど深くフードを被り、黒っぽい装束に身を包んでいる。
案内したのは領主の間に近い客間で、中庭に面した戸を全面取り払っている。
「この、掛け合いの旋律…… ケニさんは、お好きですか?」
呪術師は高く澄んだ声をしていた。彼が訪ねてきて六度目になるが、その度、他愛のないことばかりをのんびりと話をして帰っていく。
「さて。毎年聞く音に過ぎぬな」
女領主の赤茶の目は、水鏡の如く静かだった。呪術師を丁重に扱うでもなく、蔑ろにするでもなく、あっさりと問いに答える。聞き様によっては不機嫌とも取れるが、呪術師は気にする風もなかった。
「それだけ馴染み深いということでしょう。見る、聞く、肌を、体を通して感じる…… 身に染み込んでいる」
詩の一節かのように、呪術師は空に向かって諳んじた。すぅっと消えていく声は耳に心地よい。
(やれ。旅歌いのようだ)
「思い出は過ぎ去るものです。そして時々ふっと、擦れ違う」
旋律のように語る彼の口は、柔らかく、ゆっくりと音を紡ぐ。
「人は大切なものをそう沢山は抱けない。だから近所や、少し遠方にあるものも必要なんです。それが、心を広げます」
もし本当にそうだったら、女領主も気苦労を背負わずに済んだろう。呪術師が親しみやすく振る舞う奇妙さが、そんな錯覚を生んだらしい。
館の皆の不安が増し、女領主には頭が痛い。
夕暮れも近づいた時刻、庭には鶏と怪我や病気、お産が近いような羊や山羊が何頭かいるのみ。
聞き様によっては不機嫌とも取れるが、呪術師は全く気にする風もなかった。
呪術師が親しみやすく振る舞う奇妙さが、そんな錯覚を生んだのかもしれない。
人の気配もまばらな、静かな庭だった。
夕暮れも近づいた時刻、庭には鶏と怪我や病気、お産が近いような羊や山羊が何頭かいる。
外に放した家畜が、遠くで鳴くのが聞こえる。
呪術師が館の南東の、ここから右奥の場所を気にする以外は。
女領主が隣を見れば、呪術師が体を捩らせていた。
キンと鋭い音がした。
女領主は無言を貫き、ただ時折、紺の後れ毛を風に棚引かせる。その時が来るまで、彼女の水鏡は揺らがなかった。
キンと鋭い音が立つ。
そう言って呪術師は麦茶を口に含んだ。
呪術師は、女領主が無言であることを気に掛けない。
女領主がそれを眺めること暫し、ようやく、重苦しく音が漏れた。
キンと鋭い音が立つ。体を捩らせた術師の、例の術具が擦ったのだった。
呪術師を丁重に扱うでもなく、蔑ろにするでもなく、あっさりと呪術師の問いに答える。
館の皆が不安がっていることも、女領主も承知していた。
女領主に対するのは、目が隠れるほど深くフードを被り、黒っぽい装束に身を包んでいる男だった。
この、けったいな客のためだった。
案内したのは領主の間に近い客間で、中庭に面した戸を全面取り払っていた。
外で放している家畜の鳴き声が賑やかな、静かな庭だった。
大きな円形の中庭を、屋根が柵のように囲むことからついた名だった
外で放している家畜の鳴き声の方が、ずっと賑やかだった。
それを館の皆が不安がっていることも、女領主も承知している。
来る度、他愛のないことばかりをのんびりと話をして帰っていく。
(しかしまた、けったいなことになったものだ)
「……膨らんでいる」
そう言って、呪術師は女領主が注いだ麦茶を口に含んだ。
(やれ。吟遊の者のようだ)
女領主はあっさりと答える。赤茶の目は水鏡の如く静かで、輝きも揺らぎもない。不機嫌とも取れる様子に、しかし、呪術師は気を掛ける風もない。
館の皆が企み事があってかと不安がっていると、女領主も承知していた。
内容も他愛もないものばかりで、
存外聞きやすい高い声だった。呪術師は来訪の度に、こうしてのんびり話して帰っていく。
高く澄んだ声音で、呪術師は女領主に問う。女領主は濃紺の髪を風が遊ぶに任せ、誰も近寄らない回廊を眺めていた。
持成す女領主は中庭に面した戸を取り払い、麦の茶を出している。呪術師はたまに口を付けるも、ほとんど他の仕事で忙しい。
庭に放たれているのは鶏と、怪我かお産が近い羊や山羊だった。
「どうだか。この季節がくるまで、いつも忘れている旋律だ」
持成すのは女領主。
大きな円形の中庭を囲むように、その縁を屋根がなぞるのだ。
屋根はその下に2つか3つの層で部屋を持つ。その内の、会談用の客間が使われている。
ルシヤ領主の住まいは円回廊とも呼ばれ、大きな中庭を持つ円形の館だった。縁の縁を描く屋根は、その下に2つか3つの層で部屋を持っていた。
「あなたは山ほど、お持ちなんですね」
「そうであれば良いだろな」
「奏者は年ごとに音を深め、世代で色を変え、相手により違う世界を見せます」
詩でも諳んじるような調子で、呪術師は反論した。異議としてではなく、単なる意見としてだった。
女領主は感心してか呆れてなのか、一息の風を紡ぐ。
「お主の方がよほど好きそうだ」
「好きですよ。けれど、ケニさんの方が僕よりずっと馴染み深いでしょう。見る、聞く、肌を、体を通して感じる…… 身に染み込んでいる」
高く澄んだ声で、詩でも諳んじているようだった。
女領主のあっさりとした答えに、呪術師は気を掛ける風もない。
相手を見ているのは、呪術師だけ。女領主は変わらず庭を眺めていた。
女領主は客人を持成しながら、子どもの一人も近寄らない回廊を眺めていた。濃紺の髪を風が遊ぶに任せ、赤茶の目は水鏡の如く静かだ。
怪我人はすっかりただの呪術師に戻っていた。
ルシヤの館は円形で、屋根の下は2つか3つの層で部屋が造られている。その一つに会談用の客間があり、広く取られた中庭を一望できるようになっていた。
相手に向いているのは、呪術師だけ。
その中に少人数の会談用の客間があった。中庭に面した戸は全て外され、庭が一望できる。
気乗りしない様子で答えた。
この、掛け合いの様な旋律……
「身に染み込んでいるのですね」
お主の方がよほど好きそうではないか
毎年同じにはならないでしょう。
ルシヤの館は円の形で、中央は広く中庭が取られている。屋根の下は2つか3つの層で部屋が造られ、唯一層を作らないのは最奥の大広間のみだった。
この掛け合いの様な旋律を聞くと、ああ、この季節が来たのだなと思います。ケニさんは、この笛の音、お好きですか?
「ケニさんは、山羊追いをされたことはありますか」
「カチェ殿はおありか?」
女領主は群青と目も合わせず、質問に質問を返した。
「生まれついての呪術師ですので、いつも遠目に見ておりました」
呪術師はお構いなしに、のんびりと答えた。
「笛で合図しながら、自在に追い込んでいく様は見事です。細く並ばせ共に行進するところが、今まで見た中で最も美しかった」
「日追いの列のことを言っておいでか」
「さて、詳しくは。鼻から尾まで見ているわけにもいきませんから」
「日追いは日没の方角へ向かって山羊を進めさせるのだ。折り返しで集めて、星追いを始めるのだ」
「さすがにお詳しい。名手は、一等特別な人なのでしょうか」
「さて。そればかり秀でている者もいる。やれ、仕方のない」
「何かとご苦労もおありそうだ」
「それが領主というものだろう」
「いつか、ケニさんも子どもの時のように秋祭りを見られることもあるでしょうか」
「さて、な。子どもの頃など、どうしていたか」
今は全て外され一望できるようになっていた。
たまに麦茶を口に含みながら、時に風を見て、人々の営みを聞いている。
客人は呪術師、お抱えの呪い師ですら遠慮する。
たった一つ、層を作らないのが奥の領主の間で、会談や宴会でのみ使われる。その大広間の隣には、小さめの客間もあった。
中央は広く中庭が取られ、内側の縁は通路として空けられている。